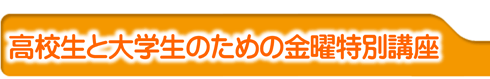

「作者の死」の歴史性
- 日時:2019年11月15日(金) 17時30分から
- 場所:東京大学教養学部18号館ホール(詳細はこちら)
- 講師:郷原 佳以
東京大学 教養学部 教養学科・准教授
【講義概要】
「作者の死」という言葉を聞いたことがありますか? もともとは、フランスの文学者ロラン・バルトが、文学作品の正当な読み方を作者の意図に求めようとする傾向を戒めるために書いた論文のタイトルです。この論文が発表されてからすでに半世紀が経ちました。強烈な印象を残すそのタイトルも手伝って、この論文は世界的に広まり、その後の文学研究の流れを方向づけるものとなりました。テクスト主義と呼ばれる潮流においては、作品読解において生身の作者のことを考慮することはほとんどタブーのようになりました。その一方、やはり作品を生み出しているのは作者だ、無視するわけにはいかない、という考えも根強く、過激なテクスト主義への反発も相俟って、見直されてきています。とはいえ、そもそも、一般の読書においては、「作者の死」はそれほど広まっているとは言えないでしょう。いずれにせよ、「作者」概念がいまでも「死んで」いないのは確かです。
しかし、往々にして忘れられがちなのは、もとのテクストです。「作者の死」がタイトルとはいっても、けっしてバルトが作者を「殺した」わけではありません。ある意味では作者はとうに「死んで」いて、彼はその歴史を整理しただけなのです。ではなぜ整理する必要があったのでしょうか。彼は1968年という時代において、いくつかの文脈のなかでこの言葉を口にしています。今回は、原典に立ち戻って、一人歩きしてきた感のあるこの概念の誕生の文脈を確認し、真の問いを探り当てたいと思います。